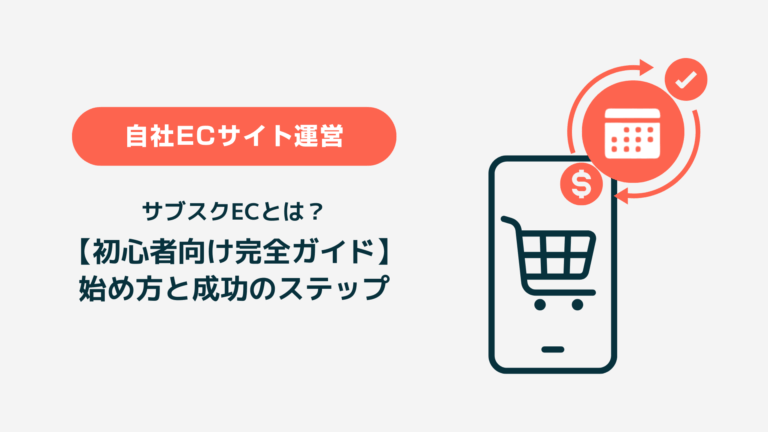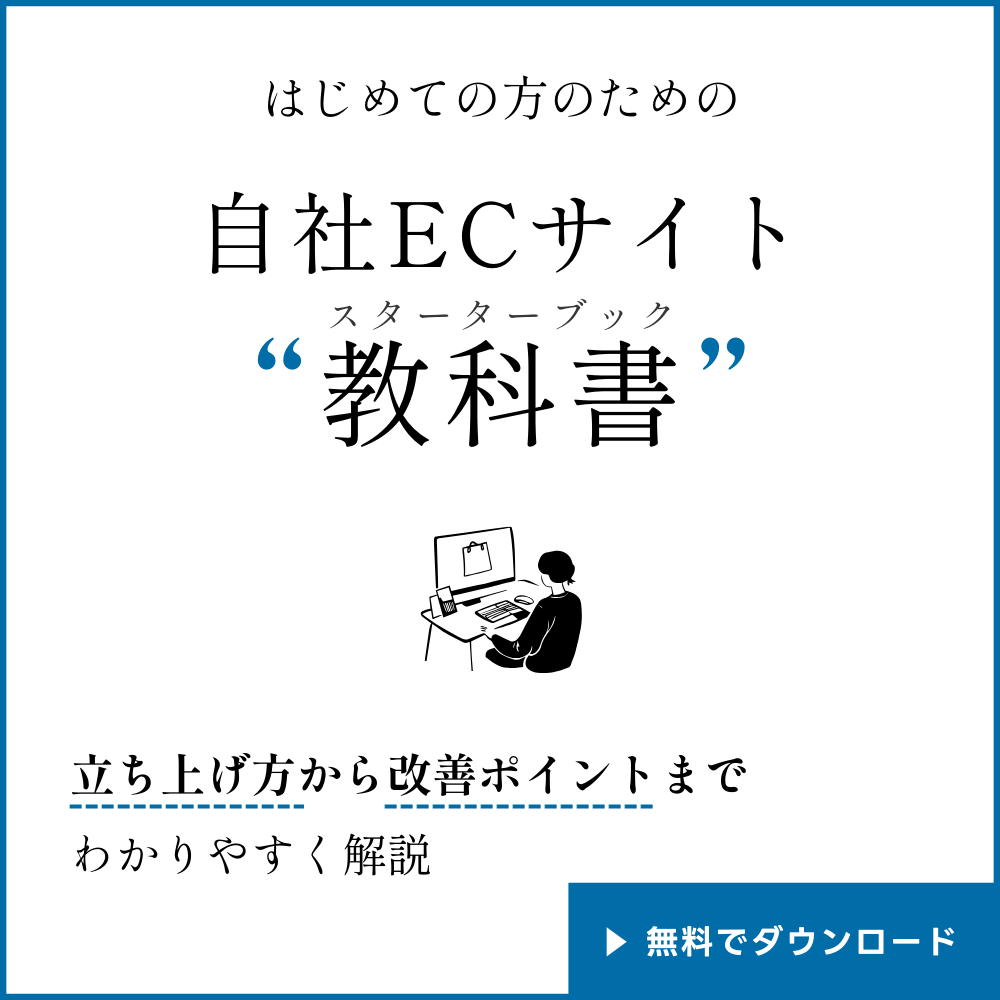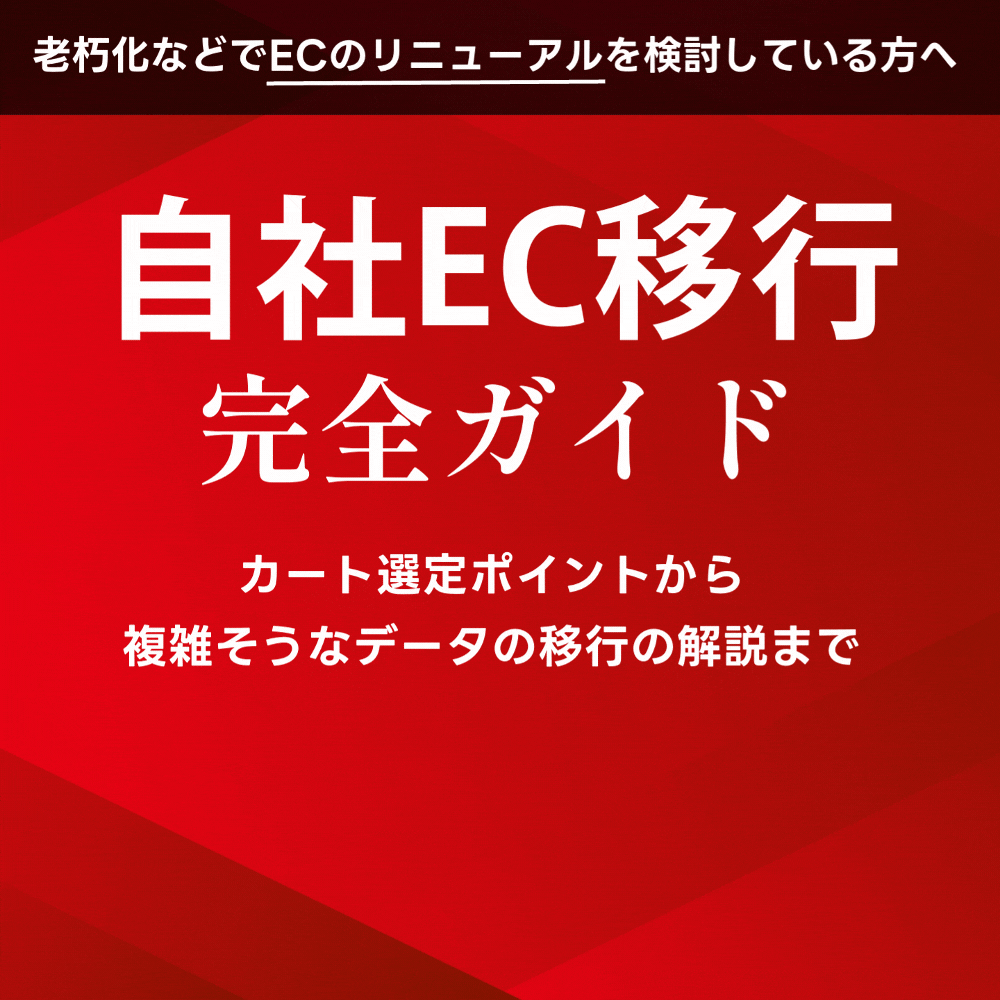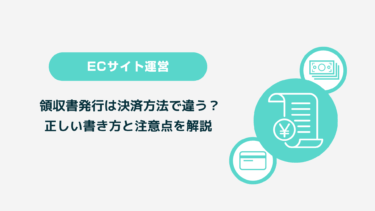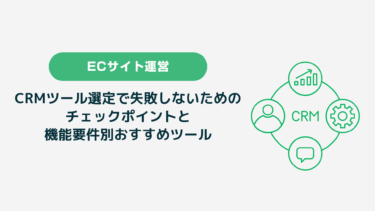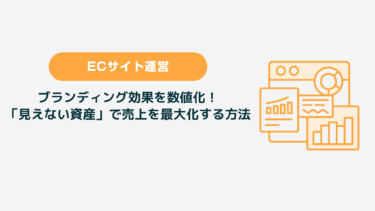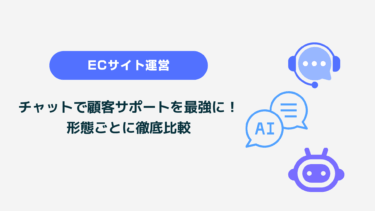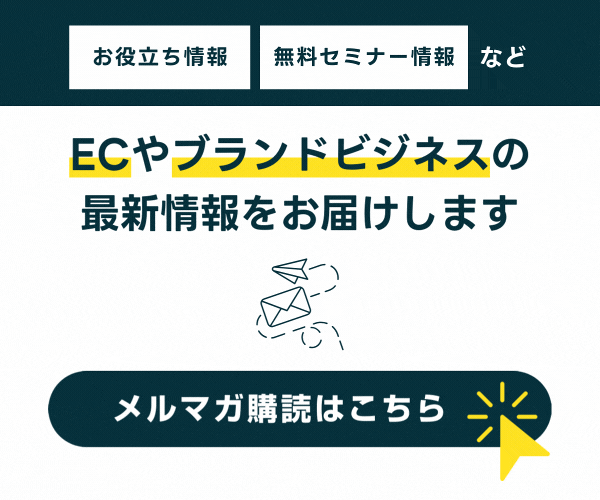こんにちは、BIZROVEです!
「売上の波をなんとかしたい……」
「LTVを最大化したい」
そのような悩みを抱えるEC事業者にとって、サブスクリプション型のEC(以下、「サブスクEC」)は大きなチャンスです。
継続的な購入を前提とするこのモデルは、収益の安定化と顧客との関係強化に強みを持ち、D2Cやリピート通販事業を展開する企業からも注目を集めています。
本記事では、サブスクECの基本から導入メリット、導入方法、成功させるためのポイントまで解説します。
サブスクECとは?その仕組みと特徴
「サブスクEC」とは、商品やサービスを定期的に提供するEC(電子商取引)の形態で、利用者は月額・年額などの定額料金を支払い続けることで継続的に商品やサービスを受け取ることができます。
例えば、以下のような形態があります。
- 化粧品の定期便
- 食品(プロテイン・野菜・ミールキット)の定期配送
- 日用品(トイレットペーパー、洗剤など)の定期補充
- ペットフードの定期配送
- ファッションレンタル
- コーヒーや日本酒の飲み比べセット
これらのビジネスは、リピーターを自然と生み出しやすく、解約しない限り継続的な売上が見込めるという特長があります。
サブスクECが向いている業界とは?
サブスクECはすべての業界に適しているわけではありませんが、以下のような特徴を持つ商品・サービスで高い効果を発揮します。
1. 日常的に消費される「消耗品」系商材
- 向いている業界例:日用品・食品・ヘルスケア・化粧品業界
- 理由:定期的な補充ニーズが発生するため、ユーザーの利便性向上と企業側の安定収益化を両立しやすい
2. 新しい体験・選択肢を提供する「体験型」商材
- 向いている業界例:ファッション(コーディネート提案)、書籍(選書サービス)、グルメ・酒類(飲み比べ体験)
- 理由:「何が届くか分からないワクワク感」や専門家によるレコメンドなど、体験価値を強調できる
3. 変化が少ない「継続利用前提」の商材
- 向いている業界例:ペットフード、健康サプリメント、プロテインなど
- 理由:同じ商品を一定の周期で使い続けるケースが多いため、「定期便化」による利便性が高く評価される
やるならどのようなサービスが良い?
たとえば、ペット用品ECサイトであれば「ペットの年齢や犬種別に最適化されたサブスクフードプラン」、化粧品なら「肌質診断×季節ごとのおすすめスキンケア定期便」など、ユーザーごとのカスタマイズ+定期性の組み合わせが鍵となります。
サブスクECのメリット
サブスクECを取り入れることで、単なる商品の販売に留まらない、持続的な成長と顧客との強固な関係性を築くことが可能になります。ここでは、その主なメリットをさらに掘り下げて解説します。
売上の安定化(LTVの最大化)
サブスクモデルの最大の魅力の一つは、売上の安定化です。一度顧客が契約すると、特別な解約がない限り、毎月あるいは定期的に定額の収益が継続的に発生します。これにより、月々の売上が大きく変動するリスクを軽減し、将来的な売上予測を立てやすくなります。
さらに、サブスクモデルはLTV(顧客生涯価値)の最大化に大きく貢献します。従来の単品販売では、顧客が商品を購入するたびにマーケティングコストが発生する可能性がありますが、サブスクモデルでは、一度獲得した顧客から長期にわたり収益を得られるため、顧客一人当たりの収益性が向上します。長期的な視点で見ると、新規顧客獲得にかかるコストを回収し、より多くの利益を生み出す可能性が高まります。
顧客との長期的な関係構築
サブスクモデルは、単発的な商品の購入で終わらない、顧客との長期的な関係構築を可能にします。定期的な商品の提供やサービスの利用を通じて、顧客との接点を継続的に持つことができるため、信頼関係を深め、ロイヤルティを高めることができます。
この継続的な接点を通じて、メールマガジンやLINE配信、同梱物、会員限定コンテンツなど、多様なコミュニケーション手段を活用することができます。顧客のニーズや嗜好に合わせた情報提供や特別な体験を提供することで、エンゲージメントを高め、ブランドへの愛着を育むことができます。また、顧客からのフィードバックを収集しやすく、商品やサービスの改善に繋げることも可能です。
マーケティング効率の向上
新規顧客の獲得は、一般的に既存顧客の維持よりも高いコストを伴います。サブスクモデルでは、既存顧客との継続的な関係を重視するため、マーケティング効率の向上が期待できます。一度獲得した顧客が長期的に収益をもたらしてくれるため、新規顧客獲得に過度に依存する必要がなくなり、マーケティングコストの最適化を図ることができます。
また、顧客データに基づいたパーソナライズされたマーケティングを展開しやすいのもサブスクモデルの強みです。顧客の購買履歴や利用状況を分析し、個々のニーズに合致した情報や提案を行うことで、より高い効果が期待できます。これにより、無駄な広告費を削減し、より効率的なマーケティング活動を展開することが可能になります。
サブスクECの始め方―導入パターンを解説
サブスクECを始める方法はいくつかあり、現在の自社の状況や目指すビジネスモデルによって最適な選択肢が異なります。ここでは代表的な3つの導入パターンを紹介します。
サブスク特化型の新サイトを立ち上げる
最も自由度が高い方法です。最初から「定期購入前提」の設計で、UIや決済フロー、顧客体験をサブスク向けに最適化できます。
- 例:スキンケアのパーソナライズ定期便サイト
- メリット:ブランディングしやすく、UX設計の自由度が高い
- デメリット:初期コストが高く、既存顧客の誘導が必要
モール型プラットフォームで定期販売を行う
Amazonや楽天市場など、モール内の定期購入メニューを活用する方法です。
- Amazon:「定期おトク便」などの仕組みを活用
- 楽天市場:「定期購入型商品」設定が可能(出店条件あり)
- メリット:既存の集客力がある
- デメリット:サブスク体験の柔軟性が乏しい、手数料が高い
既存のECサイトにサブスク機能を追加する
現在運用中の自社ECに、サブスク機能を後付けする方法です。定期課金や配送間隔の管理機能を追加することで、通常の単品購入と併用できます。
- メリット:既存の顧客基盤を活かせる/システム開発を最小限にできる
- デメリット:UI調整や運用フローの再設計が必要なケースもある
| 導入パターン | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 新サイト立ち上げ | ブランディングの自由度が高い、独自のUX(ユーザーエクスペリエンス)を設計しやすい | 初期コストが高い傾向がある、新規顧客の獲得が必要となる、既存顧客への告知と誘導が必要 |
| ECモール | モールが持つ既存の集客力を活用できる、比較的容易に導入できる場合がある | サブスクリプション体験の柔軟性が低い、手数料が発生する、顧客データやブランドイメージのコントロールが自社ECほど自由ではない |
| 既存のCサイトへのサブスク機能追加 | 既存の顧客基盤を活かせる、比較的低コストかつスピーディに導入できる可能性がある、単品販売との併用が可能 | UIの調整や運用フローの再設計が必要となる場合がある、既存システムの制約を受ける可能性がある |
リスクを抑えつつ、着実にサブスクリプションモデルを導入したい場合、既存のECサイトにサブスクリプション機能を追加する方法が現実的かつ効果的な第一歩と言えるでしょう。
既存顧客という貴重な資産を活かしながら、新たな収益源を確保し、顧客との関係性をより深化させることができます。
もちろん、将来的なビジネスの成長戦略によっては、サブスクリプション特化型の新サイト立ち上げも視野に入れるべき選択肢となり得ます。しかし、まずは既存の自社ECサイトにサブスクリプション機能を導入し、その効果を検証しながら、段階的にビジネスを拡大していくのが賢明なアプローチと言えるでしょう。この方法であれば、初期投資を抑えつつ、サブスクリプションモデルのメリットを享受することができるはずです。
既存の自社ECサイトへのサブスクリプション機能の導入方法
自社ECサイトにサブスクリプション機能を導入する方法は、利用しているプラットフォームによって異なります。ここでは、主要なECプラットフォームにおける機能追加の方法と、より具体的な情報を提供します。
Shopify
Shopifyは、豊富なアプリストアを通じて、サブスクリプション機能を比較的容易に追加できるのが特徴です。
- Shopifyアプリの活用:
- 定期購買:豊富な機能を持ち、とくに日本語によるサポートが手厚く、他のアプリとの連携にも強みがあるため、既存のシステムとの連携を重視する場合におすすめです
- Mikawaya Subscription:ストアの売上向上に特化した機能と、きめ細やかな日本語サポートが特徴で、詳細なデザインカスタマイズも可能なため、ブランドイメージを重視するストアに適しています
- Shopify Subscriptions:Shopifyが公式に提供する完全無料のアプリで、シンプルな設定で基本的な定期販売機能をすぐに利用開始できます
- 導入の容易さ:アプリストアからインストールし、簡単な設定を行うだけでサブスクリプション販売を開始できる場合が多く、プログラミングの知識がなくても導入しやすいのが魅力です
- 注意点:アプリによっては月額費用が発生します。また、既存のテーマとの互換性や、必要な機能が揃っているかなどを事前に確認することが重要です
| アプリ名 | 無料プラン | 有料プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 定期購買 | テストのみ | $49/月〜 | 高機能、日本語サポート、外部連携に強み |
| Mikawaya Subscription | テストのみ | $12/月〜 | 売上向上特化、日本語サポート、詳細なカスタマイズ性 |
| Shopify Subscriptions | 無料 | – | Shopify純正、基本的な機能 |
※アプリの料金プランや機能は変更される可能性があります
BASE
BASEは、「定期便App」を利用することで、ノーコードで手軽にサブスクリプション販売を始められるプラットフォームです。
- 定期便Appの機能:
- 簡単な設定:商品と配送頻度、価格などを設定するだけで、定期購入オプションを商品ページに追加できます
- 自動決済:設定したサイクルで自動的に決済が行われます
- 購入者管理:定期購入の購入者リストや注文履歴などを管理できます
- 導入の容易さ:プログラミングの知識は一切不要で、BASEの管理画面から数クリックで設定が完了します。手軽にサブスクリプションを試したい場合に最適です
- 注意点:提供される機能は比較的シンプルであり、高度なカスタマイズや複雑な定期購入プランには対応できない場合があります
Makeshop
Makeshopでサブスクリプション機能を導入するには、主に以下の方法があります。
- 定期購入オプション機能(標準機能またはApp):
- Makeshopのプランによっては、標準機能として定期購入オプションが提供されている場合があります
- また、「Makeshop App Store」にて、定期購入機能を提供するアプリが提供されている場合もあります
- 外部連携:
- 外部のサブスクリプション管理ツールと連携することで、高度な定期購入機能を実現できます。連携には、API連携などの設定が必要となる場合があります
- カスタマイズ開発
- 自社の要件に合わせて、個別にプログラミング開発を行うことも可能です。この方法は柔軟性が高い反面、時間とコストがかかります
- 導入の注意点:利用プランによって利用できる機能やアプリが異なる場合があります。外部連携やカスタマイズ開発には専門知識が必要となる場合があります
カラーミーショップ
カラーミーショップでサブスクリプション機能を導入する場合、主に以下の方法が考えられます。
- 外部サービス連携:
- 外部のサブスクリプション管理サービスと連携する方法が一般的です。これらのサービスを利用することで、定期購入の受付、決済、顧客管理などを行うことができます。
- 連携には、各サービスの提供するコードをショップに埋め込むなどの作業が必要となる場合があります。
- カスタマイズ開発:
- APIなどを利用して、自社でサブスクリプション機能を開発することも可能です。高度なカスタマイズが可能ですが、専門知識と開発リソースが必要です。
- 導入の注意点:外部サービスとの連携には、別途契約や費用が発生する場合があります。カスタマイズ開発は技術的なハードルが高いです。
EC-CUBE
EC-CUBEはオープンソースのECプラットフォームであり、サブスクリプション機能を導入するには主に以下の方法があります。
- プラグインの利用:
- EC-CUBEの公式またはサードパーティ製のプラグインを利用することで、定期購入機能を追加できます。様々な機能を持つプラグインが存在するため、自社の要件に合ったものを選択できます。
- カスタマイズ開発:
- EC-CUBEのソースコードを直接編集したり、独自のプラグインを開発したりすることで、柔軟なサブスクリプション機能を実装できます。
- 外部連携:
- 外部のサブスクリプション管理システムと連携することも可能です。
- 導入の注意点: プラグインの導入やカスタマイズ開発には、ある程度の専門知識が必要となる場合があります。プラグインの互換性やセキュリティにも注意が必要です。
このように、各ECプラットフォームには、それぞれの特徴に応じたサブスクリプション機能の導入方法が存在します。自社の技術力や予算、必要な機能などを考慮して、最適な方法を選択することが重要です。
サブスクECを成功させる方法―中長期的に売上を伸ばすポイント
サブスクECは一度始めれば自然と安定収益が積み上がる…というものではありません。むしろ、導入後の運用次第で成果に大きな差が出ます。ここではサブスクECを成功させるための代表的な取り組みを紹介します。
初回体験の満足度を最大化する
サブスクビジネスでは、最初の1回目の配送体験や商品品質が、継続率に大きく影響します。開封体験や同梱物、パーソナライズなど「想像以上」の要素を初回に詰め込むことで、2回目以降の継続につながります。
- 例:初回は通常より多めのボリューム/使い方ガイド同梱/手書きメッセージなど
商品・プランを継続利用しやすく設計する
サブスクは「毎月届く」ことが価値である一方で、「もう使いきれない」「在庫が余る」となると一気に解約されてしまいます。
- プラン例:隔月/3ヶ月に1回などの柔軟な配送間隔
- サービス例:「次回スキップ」「一時停止」機能の実装
ユーザーのライフスタイルに合わせた「ちょうどいい頻度と量」を提供することがカギです。
チャーンレート(解約率)を下げる施策を徹底する
継続的に収益を得るサブスクECにおいて、最も重要な指標の一つがチャーンレート(解約率)です。どんなに初回獲得がうまくいっても、数ヶ月で解約されては利益が伸びません。
以下のような工夫が、チャーンレートの改善に効果的です。
- ユーザーごとの継続率分析とフォローアップ
例:2回目の利用で解約しやすい傾向があれば、そのタイミングでクーポンや特別案内を送付 - 解約理由のヒアリングと反映
解約時にアンケートや選択式で理由を取得。例えば「在庫が余る」なら間隔調整オプションを追加 - 解約手続き画面で「引き留め」施策
解約ページで「一時停止」や「次回スキップ」の選択肢を提示する企業も多く見られます - 定期的な情報発信・価値訴求
メールや同梱チラシで「商品の魅力」や「他の活用方法」を定期的に伝え、利用意欲を保ちます
チャーンレートの改善は「LTV(顧客生涯価値)」の最大化につながるため、サブスク事業における最重要KPIの一つとして捉えるべきです。
データを活用して改善サイクルを回す
「定期購入」という性質上、ユーザーの行動データが非常に蓄積しやすいのがサブスクの強みです。以下のようなデータを活用し、継続率や満足度を高めていくことが重要です。
- 継続回数別の離脱傾向(例:3回目での解約が多い)
- 購入プランごとのLTV比較
- ユーザーの属性と継続傾向の相関分析
BIツールやGoogleアナリティクス、MAツールの活用によって、改善のヒントを得ることができます。
まとめ
サブスクECは、数多くのメリットをEC事業にもたらします。定期的な収益が見込めることで事業計画が立てやすくなり、顧客との継続的な接点はロイヤルティを高め、結果として顧客生涯価値(LTV)の最大化に繋がります。
また、一度獲得した顧客との関係性を深めることは、新規顧客獲得に比べコスト効率の良いマーケティング戦略と言えるでしょう。
ただし、サブスクECの導入は、ECサイトの出店状況や事業のフェーズによって最適なアプローチが異なります。新規に特化サイトを立ち上げる、既存のモールを活用する、あるいは現在運営している自社ECサイトに機能を追加するなど、それぞれの方法にはメリットとデメリットが存在します。
重要なのは、サブスクECの持つ可能性を理解した上で、自社の顧客層、提供する商品・サービス、そして事業の成長戦略を慎重に検討し、最適な導入方法を選択することです。
ACROVEでは、サブスクECに対応した自社ECサイトの構築や、既存ECサイトのサブスクEC導入を支援しています。
サブスクECをご検討されている方は、以下のバナーよりぜひACROVEまでご相談ください!